西海市2泊3日 キャンプ登山の旅 その14
音浴博物館にて

西海市の観光スポットを検索していて、ぜひ行きたい場所を見つけました。
『音浴博物館』は、私が計画書に『温浴博物館』とタイプミスをしていたために、家族は温泉関係の場所かと勘違いしていたようです。それは、山間の小さな分校の跡地にありました。




日曜日という休日ではありましたが、私たちが訪れた時には、来訪者が私たちだけということもあり、この音浴博物館の歴史から、レコードの歴史等をていねいに説明していただきました。また、音に関する薀蓄もいろいろと聞かせていただき、特に若いころから自称オーディオマニアだった私にとっては、とても興味ある展示物と説明に感激した次第です。
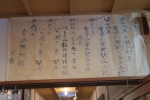


廃校になった小学校の校舎を再利用して、倉敷市にあった施設の中身をそっくり移設したものだということです。なんと10tトラック40台分にもなる膨大な量だったというから驚きです。
SPレコード時代からアナログレコードへ…そして最近のデジタルのCDに至るまでの音に関する歴史がつまっている場所でした。
エジソンの蝋管レコードの説明から、SPレコードの台頭、電気信号によるアナログレコードの原理とか、回転数やドーナツ盤ができた経緯など、わかっていたようで知らなかったこともいろいろ知ることができ、短時間の説明でしたが、私にはとてもよく分かりました。




中でも、SP盤には、僅かな時間分の楽曲しか収録できないことから、交響曲1曲とか、何曲もの曲を1つにまとめたものは、数枚入りのセットにして作成することになり、「その外観から『アルバム』と呼ぶようになった。」と言う話には目から鱗でした。また、ステレオセットの説明の際、まだ、FMステレオ放送が開始される以前に、かつて「MWバンド」と言われる中波の放送でNHKがラジオ第1放送と第2放送の電波でLchとRchを別々に同時に流して、ステレオ放送をしていたことがあったという話をその時のステレオセットの現物前にして説明していただき、先人の音に関する追求する力に感動しました。
同行した息子は、現在、21歳ですが、すでにCD以降の世代。自宅のオーディオセットには、アナログのレコードプレーヤーが乗っかってはいますが、私さえもそれを動かしたのはもう20年近く前になるような…なので、息子にとっては何もかもが未知の話だったのではないかと思います。



また、こちらには、あこがれのJBLのスタジオモニター4344やタンノイのスピーカーをマッキントッシュ(McIntosh)のセパレートアンプで鳴らす視聴ルームがあるのです。しかもこの施設には、アナログのレコードが、あらゆるジャンルで、なんと16万枚も所蔵されていて、それが自由に視聴できるのでした。ハイレゾにももちろんそのよさはあるとは思いますが、数100万円のオーディオシステムで鳴らすアナログレコードの調べにも深い味わいがあります。いつまでも聴いていたいと思えるような素敵な音色でした。
その後、2~3グループの方々が来られていましたが、年代的には私と近いか少し歳上の方々でしたね。皆、懐かしさをしっかり感じながら展示を見学されていました。
意外にもかみさんに大好評でして、若いころに大ファンだったというガロ(…「学生街の喫茶店」のヒットで記憶にある方もいるかしら?) のアルバムを見つけてきて「懐かしい!」と聴き入っていました。
そして、「絶対もう一度訪れたい」と・・・秋のキャンプの候補地が決まりました。
ぼちぼち綴っていきます。



西海市の観光スポットを検索していて、ぜひ行きたい場所を見つけました。
『音浴博物館』は、私が計画書に『温浴博物館』とタイプミスをしていたために、家族は温泉関係の場所かと勘違いしていたようです。それは、山間の小さな分校の跡地にありました。




日曜日という休日ではありましたが、私たちが訪れた時には、来訪者が私たちだけということもあり、この音浴博物館の歴史から、レコードの歴史等をていねいに説明していただきました。また、音に関する薀蓄もいろいろと聞かせていただき、特に若いころから自称オーディオマニアだった私にとっては、とても興味ある展示物と説明に感激した次第です。
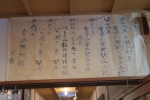


廃校になった小学校の校舎を再利用して、倉敷市にあった施設の中身をそっくり移設したものだということです。なんと10tトラック40台分にもなる膨大な量だったというから驚きです。
SPレコード時代からアナログレコードへ…そして最近のデジタルのCDに至るまでの音に関する歴史がつまっている場所でした。
エジソンの蝋管レコードの説明から、SPレコードの台頭、電気信号によるアナログレコードの原理とか、回転数やドーナツ盤ができた経緯など、わかっていたようで知らなかったこともいろいろ知ることができ、短時間の説明でしたが、私にはとてもよく分かりました。




中でも、SP盤には、僅かな時間分の楽曲しか収録できないことから、交響曲1曲とか、何曲もの曲を1つにまとめたものは、数枚入りのセットにして作成することになり、「その外観から『アルバム』と呼ぶようになった。」と言う話には目から鱗でした。また、ステレオセットの説明の際、まだ、FMステレオ放送が開始される以前に、かつて「MWバンド」と言われる中波の放送でNHKがラジオ第1放送と第2放送の電波でLchとRchを別々に同時に流して、ステレオ放送をしていたことがあったという話をその時のステレオセットの現物前にして説明していただき、先人の音に関する追求する力に感動しました。
同行した息子は、現在、21歳ですが、すでにCD以降の世代。自宅のオーディオセットには、アナログのレコードプレーヤーが乗っかってはいますが、私さえもそれを動かしたのはもう20年近く前になるような…なので、息子にとっては何もかもが未知の話だったのではないかと思います。



また、こちらには、あこがれのJBLのスタジオモニター4344やタンノイのスピーカーをマッキントッシュ(McIntosh)のセパレートアンプで鳴らす視聴ルームがあるのです。しかもこの施設には、アナログのレコードが、あらゆるジャンルで、なんと16万枚も所蔵されていて、それが自由に視聴できるのでした。ハイレゾにももちろんそのよさはあるとは思いますが、数100万円のオーディオシステムで鳴らすアナログレコードの調べにも深い味わいがあります。いつまでも聴いていたいと思えるような素敵な音色でした。
その後、2~3グループの方々が来られていましたが、年代的には私と近いか少し歳上の方々でしたね。皆、懐かしさをしっかり感じながら展示を見学されていました。
意外にもかみさんに大好評でして、若いころに大ファンだったというガロ(…「学生街の喫茶店」のヒットで記憶にある方もいるかしら?) のアルバムを見つけてきて「懐かしい!」と聴き入っていました。
そして、「絶対もう一度訪れたい」と・・・秋のキャンプの候補地が決まりました。
ぼちぼち綴っていきます。


